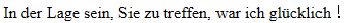夢とも現実ともつかない時を過ごした僕らが、元通りとはいかないまでも、日常と呼べるような時間を取り戻した頃だ。
いつものように僕が食事を作り、いつものようにアスカが食卓についた。今日はまだミサトさんが帰っていないので、ここにいるのは僕とアスカだけ。
本当ならこの場にはミサトさんもいるはずで、ミサトさんがいるときは、誰よりも早く食卓についている。
アスカと二人の食事は賑やかなものではないけれど、決して居心地の悪いものではなかった。それどころか今の僕はアスカと二人で過ごす、この時間が好きだ。
最近のアスカは以前のアスカとは何か違う。
前のように僕に突っ掛かることもないし、無言の圧力をかけてくることもない。買い物にもよく付き合ってくれるようになったし、この前なんか皿洗いまで手伝ってくれた。
僕たちの身に起きた不幸な出来事の数々は、それはひどく苦しいものであったのは間違いないけれど、あの時間がなかったら、こんなに心穏やかな時間が訪れることはなかったはずだ。
あの悪夢のような出来事でさえ、僕らには必要な時間だったのだ。
僕がミサトさんの家に来てどのくらい経ったのか。アスカと僕は、この家でどれくらい同じ時を過ごしたのか。
どれだけの時間を笑顔で過ごし、どれだけの夜を眠れずに過ごしたのか。
今となっては、どうでもいい。
だって、僕はやっと僕の居場所を見つけたのだから。
新しい関係を築き始めている僕らは、きっと仲良く暮らしていける。
僕は初めて感じる、そんなくすぐったいような、気恥ずかしいような気持ちで、目の前に座るアスカを眺めた。
ふと顔を上げたアスカと目が合う。
「何よ?」
「ううん、何でもない」
そんな他愛もないやりとりが、日常を感じさせてくれた。僕が望んでやまなかった、ささやかな日常を。
ずっとこのままでいられると思っていた。ずっとみんなでいられると信じていた。
それなのに……
突然の思いがけないアスカの一言が、そんな僕らの日々に終止符を打ったんだ。本当に突然だったんだ。
***
「アタシ、ドイツへ帰るから」
「え!?」
アスカは僕の作ったハンバーグを口に放り込みながら、明日の天気でも話すように、当たり前の顔でそう告げた。
「ドイツって、バームクーヘンのドイツ?」
「アンタ、馬鹿にしてるの?」
あまりにも驚いて思わず意味不明な返事をしてしまった僕に、アスカが突き刺すような視線を寄越す。
「ち、違うよ。急にそんなこと言うから、びっくりして……」
「もう決めたの。ごちそうさま」
いつ? なんで? どうして?
そんな簡単な質問さえできなかった。頭が真っ白だったから。アスカの一言は、僕の思考を停止させるのに十分なだけの威力を持っていた。
やっと僕たちの居場所を見つけたのに。みんなで楽しく暮らしていけると思ってたのに。
これからもずっと。ずっと三人で。
僕は呆然としたまま、自分の部屋へ戻って行くアスカの背中を見送る。
アスカは違ったの? ここはアスカの居場所じゃないの? やっぱり僕のこと嫌いなの?
我に返った僕は手にしていた茶碗と箸を放り出すようにテーブルに置くと、慌ててアスカの部屋の戸の前に駆け寄った。
「アス……」
ノックしかけて、止めた。
アスカには聞きたいことがいっぱいある。
「いつドイツへ行っちゃうの?」
「なんでここじゃダメなの?」
でもだからって、僕はそれを聞いて何て答えたらいいんだろう。
「そうなんだ」
僕にはたぶん、そんな答えしかできない。気の利いた返答のひとつもできない僕は、またアスカを失望させるだけだ。
だから僕なりに考えた。一晩中考えた。考えて、考えて、そして朝になった。
そうして出したひとつの結論。
アスカは僕のことを赦してくれていない。
僕にはそれしか考えられなかった。僕はアスカに一生かかっても償いきれないほど酷いことをしたのだから。どんなに謝っても薄れることのない深い傷を、アスカの心に負わせてしまったのだから。
自分でもわかってるのに、それでもアスカのそばに居たいと思うのは、アスカにそばに居て欲しいと願うのは、僕の我が儘なんだよね。アスカには辛いだけなんだよね。
小さな頃からエヴァのパイロットになるためだけに頑張ってきたアスカが、やっとエヴァから解放されたんだ。エヴァのない世界になったんだ。
これからは、アスカはアスカのために時間を使うべきで、何にも縛られず、誰にも命令されず、自分の願う通りに、自分の思う通りに生きる番なんだ。
そんなこと僕にもわかってる。十分わかってるんだよ。
だからアスカを自由にしてあげなきゃいけないんだ。アスカの意志を尊重して、アスカをドイツに帰らせてあげなくちゃいけないんだ。
だって、だってさ、僕にはないんだよ。どんなに辛くても、それだけはしちゃないけないんだ。これ以上、アスカに辛い思いをさせちゃいけないんだ。
わかってる。
散々アスカを傷つけてきた僕に、アスカを引き止める資格なんて少しもない。
***
アスカからドイツへ帰ることを聞かされた翌日、ミサトさんに呼び出された。
NERVではない、元NERVと呼ぶのが相応しい組織にミサトさんはいる。NERVの後始末をするのが目的の組織だ。
名称も建物も役割もすっかり変わってしまったけど、僕は好んで"元NERV"と呼んでいる。赤い海から戻らなかった父さん以外、ほとんど顔ぶれの変わらないみんながいるから。
それに新しい名称を使うと、そこが全く知らない場所に聞こえて、なんか居心地悪いんだ。
その"元NERV"の会議室で今、ミサトさんは改まった顔をして、僕と向かい合って座っている。
「アスカに聞いた?」
僕は返事をする代わりに、小さく頷いた。それにつられるようにミサトさんも小さく2〜3度頷き、そして「はぁ」と大きく息を吐いた。
「寂しくなるわね」
「はい」
自分で僕を呼び出したくせに、ミサトさんはそれだけ言って黙りこんだ。
一点を見つめたまま、いや、ミサトさんの視線はどこにも向かってなくて、ただ目を開いているだけのようだ。
いつもとは違うミサトさんの雰囲気に緊張し、僕はおもむろに姿勢を正す。
しばらくの沈黙の後、ミサトさんが重々しく口を開いた。
「私もね、昨日聞かされたのよ」
「えっ」
ハッと顔を上げた僕に向かって微笑んだミサトさんの顔は、笑っているのにひどく悲しそうで、今にも泣きだしそうに見えた。
「昨日突然私のところにやって来て『ドイツへ帰ることにしたから』って。『ドイツへ帰ろうと思うんだけど』じゃなくて、『ドイツへ帰ることにしたから』って言うのよ」
「……」
返す言葉が見つからなかった。ミサトさんの表情を見ればわかるから。
ミサトさんも僕と同じで、アスカがいなくなることがまだ信じられないんだ。
「あの、それでアスカはなんで」
「教えてくれないの」
アスカの帰国の理由を聞こうとした僕の言葉を最後まで聞かずに、ミサトさんは答えた。
「ドイツが恋しくなったからって、それ以外は何も言わないのよ、あの子。でも本当の理由は別にあると思うの。だってあまりにも突然すぎるもの」
また寂しそうな顔。
ミサトさんは話して欲しかったに違いない。アスカもそれはわかっているはずなのに、なのに何で相談しなかったんだろう。何の役にも立たない僕は未だしも、ミサトさんには話してあげて欲しかった。
ミサトさんの寂しそうな様子を見るのが辛い。顔は笑っているけれど、瞳の奥で揺れる悲しみの色は僕にもはっきり見てとれる。
ミサトさんのこんな姿、初めて見た。
「あの、それでアスカはいつドイツへ帰るんですか?」
ミサトさんがひどく驚いた顔をする。
「嫌だ、アスカったら本当に何も話してないの?」
「あ、アスカはドイツへ帰るとしか言わなかったから」
「まったくあの子ったら」
少し俯き加減で額に手を置くと、ひどく言いにくそうに唇を噛んだ。
「それなんだけど……」
言い淀むミサトさんを前に、「大丈夫だから」という気持ちを込めて大きく頷き、先を促す。
「それがね」
「はい」
「5日後なの」
「えっ?」
「5日後の17時の便を予約したらしいの」
「えっ……?」
別にミサトさんが悪いわけじゃないのに、ミサトさんが申し訳なさそうな瞳で僕を見る。
だからミサトさんには言っても仕方ないのに、でも言わずにはいられなかった。
「5日後ってそんな、そんなのすぐじゃないですか! アスカは何で、そんな、相談もなしに何でそんな急に」
こんなの、ただの八つ当たりだ。
ミサトさん、ごめん。
僕たちの間に、再び沈黙が訪れた。ミサトさんも僕も、気持ちは同じだったから。何も言わなくても、お互いの気持ちが痛いほど想像できるから。
僕はフラフラと立ち上がり無言で会議室を後にした。ミサトさんはチラッと顔を上げたけど、もう何も言わなかった。
足が重い。家に帰ってアスカの顔を見て、僕は何を話したらいいんだろう。一歩ずつ確実に家に近づいていくのに、心は会議室に忘れてきてしまったみたいに空っぽだ。
何から考えていいのかわからない。心は空っぽだけど、頭は今にもパンクしそうだった。
これはきっと僕が事実を受け入れるために必要な時間なんだろう。でもそれはあまりにも複雑で難解で、受け入れて理解するためには時間が短過ぎる。僕にもミサトさんにも、もっともっと時間が必要なんだよ。
だからさ、そんなに急いでドイツへ帰るなんて言わないでよ。僕もミサトさんも、アスカがいなくなるなんて考えたこともないんだから。
なんでそんなに急いで帰らなくちゃならないんだよ? 僕もミサトさんも、5日じゃ無理だよ。アスカがいなくなることを受け入れるなんて無理だよ。
せっかく平和な世の中になったのに。もうエヴァに乗らなくていい世界になったのに。委員長やトウジやケンスケと、これからいっぱいいろんなことできるんだよ。みんなで一緒に普通の学生生活を送れるんだよ。
なのに何でなの? 何でドイツなの? 何で日本じゃダメなの? どうしてみんなと一緒にいられないの?
アスカ? ねぇ、アスカ?
アスカはやっぱり、僕のことが嫌いなの……?
***
家に着いた僕は、昨日までと同じように、何事もなかったかのように夕食の支度を始めた。
味噌汁に入れるための大根を短冊切りにして、油揚げを湯通しする。
頭で考えなくても身体が勝手に動いてくれる。このときほど習慣をありがたいと思ったことはない。
僕が帰ってきたときアスカはリビングにいた。そして昨日の話なんかまるでなかったかのように、いつもと同じようにチラッと僕の存在を確認し「おかえり」と表情ひとつ変えないでいる。
そんな風にされたら僕もいつも通りにするしかなくて、でもまだ戸惑いも、そしてなぜだか悔しさもあって、僕はアスカの顔も見ずに「ただいま」と小さく言い部屋に飛び込んだ。
どんな顔をしていいのかわからないし、どんな風に話しかけていいのかもわからないから。
アスカは僕にあれこれ聞かれるのが嫌で、何事もなかったような顔をしている。アスカの背中が僕に向かって言ってる。
「何も聞かないで」
だから僕は静かにキッチンに立った。そしていつものように夕食の支度を始めた。
アスカが日本にいる時間があと数日しかないのなら、せめてその間だけでも精一杯おいしいご飯を作ってあげたい。そしてできるなら、ほんの少しでいいから僕のことを覚えていて欲しい。
そして叶うなら、もしも叶うなら、ただ一瞬でいい。僕のことを赦して欲しい。
そうなんだ。僕には反対する権利も資格もない。
だから僕はただアスカの意思を尊重する。アスカの希望が最優先されるべきだから。例えそれが僕にとって辛いことであっても苦しいことであっても、僕はそれを甘んじて受けなければならない。
だってそれが神様が僕に与えた罰だから。
それでもまだ、僕がアスカに対して犯した罪は到底償えない。
何度も何度も繰り返してきた二人での食事を、こんなに苦しいと思ったことはなかった。早く帰ってきてくれないミサトさんを心底恨んだ。
アスカはずっと押し黙ったまま。僕も何を話していいかわからず、それどころかアスカの顔をまっすぐ見ることさえできないでいる。
一生懸命作った食事も、砂を噛むように味気ない。
でもこれじゃ駄目だ。アスカの望む別れは、きっとこんなんじゃない。
いつもように、何事もなかったように、アスカの望むように、アスカを送り出してあげなきゃいけないんだ。
心の内で小さく決意した僕は、思い切って声を出した。
「あ、あのさ」
「なによ」
「きょ、今日は和食にしたんだ。ドイツへ帰ったら和食を食べる機会もなくなっちゃうんじゃないかなって。だから和食にしたんだけどどうかな。この魚の煮付け、なかなか上手に出来てると思うんだけど。あ、そうだ。アスカの食べたいものあったら何でも言ってね。アスカの食べたいもの、何で作ってあげるから。日本でしか食べられないものもあると思うし。ドイツに帰って食べたくなっても、材料そろえるのもきっと難しいと思うし、それに……」
人って困ったことや焦ったことがあると、本当に口が止まらなくなるんだね。知らなかったよ。
僕の口が勝手にしゃべり続けてる。止められないや。
自分の口から出て行くたくさんの文字たちを、他人の言葉みたいにぼんやりと耳で聞いていた時だった。突然大きな音をたてて、アスカが手にしていた箸をテーブルに叩きつけた。
「アンタ」
「えっ」
「他に何か言うことはないの?」
アスカが大きな瞳をさらに大きく見開いて、僕を睨みつけている。
「えっ?」
「アタシに言いたいことはないわけ?」
「えっ」
「ないの?」
「ないわけじゃ」
「じゃあなんで聞かないのよ?」
アスカにしては珍しく静かに感情を押し殺した話し方をしていたけど、それがかえって僕の癇に障った。
なんで?
だってアスカが聞いて欲しくないような顔をしていたんじゃないか。昨日だって僕を寄せ付けないように部屋に閉じ込もってたし、さっきだって何もなかったような顔をしてたじゃないか。ミサトさんにもろくに話をしなかったアスカに、僕がなんて聞けばいいんだよ。僕に話す気なんかないくせに。話す気があるなら、昨日のうちに話してるはずじゃないか。
じゃあ、アスカは聞いたら教えてくれるの?
なんでも答えてくれるの?
「いつドイツへ発つのか」って。「どうして急にドイツへ帰ることにしたのか」って。「もう少し日本にいられないのか」って。「なんでミサトさんにも相談しなかったのか」って。
「やっぱり僕のことが嫌いなの?」って。
「……いつ出発するの?」
震える声を隠すように、小さく低い声でつぶやいた。
「土曜日の夜17時の便」
「すごく急だね」
「そうね」
「なんでドイツに帰ることにしたの?」
「別に。ちょっとドイツが恋しくなっただけ」
「今じゃなきゃ駄目なの?」
「今帰りたいの」
「もう少し日本にいればいいのに。きっとみんな寂しがるよ」
「うるさいのがいなくなって清々するんじゃない?」
「そんなことないよっ!」
自分が思ったよりもずっと大きな声を出してしまったみたいで、アスカが少しビクッとしたのがわかった。恥ずかしくなって僕は慌てて付け加える。
「あ、あの、そういえばミサトさんにも相談しなかったんだってね」
「ミサトに言ってどうするのよ。ドイツに帰るか日本に残るかなんて、人が決めることじゃないもの」
「そうかもしれないけど、ミサトさんはアスカが何も話してくれなかったことがすごくショックだったみたいだよ」
アスカは大げさに肩をすくめて見せた。
「ミサトに話してもどうにもならないもの」
「どうにもならないって、アスカ、何か困ったことでもあったの? それなら尚更ミサトさんに相談したほうがいいよ。ミサトさんならきっとなんとかしてくれるよ。きっとミサトさんなら……」
ふと気づくと、アスカがとても悲しそうな目で僕を見ていた。睨みつけるのではなく、ただ静かに僕の顔をじっと見てる。
「アンタに言ってもしょうがない」
アスカの目がそう言っていた。
「どうにもならないのよ」
最後にそれだけポツリと言うと、アスカは席を立った。
なぜか僕にはアスカの声が少しだけ震えているように聞こえた。
***
5日なんてあっと言う間だった。
あれ以来、アスカは極端にドイツの話を避けるようになり、結局あの日に聞いた以上のことは何も教えてくれなかった。それはミサトさんも同じで、僕もミサトさんもモヤモヤした気持ちを抱えたまま今日までを過ごしてきた。
そんな僕たちの気持ちを知ってか知らずか、アスカは毎日楽しそうに荷造りをし、学校や旧ネルフのみんなが開いてくれた送別会では笑顔を絶やさなかった。
アスカはドイツに帰るのが本当に嬉しいんだ。
僕はもうアスカの帰国の理由を無理に聞き出そうとは思わない。こんなに嬉しそうなアスカの顔を見たのは、もしかしたら初めてかもしれないから。
そうか。アスカにとって日本とはそういう場所なんだ。笑顔を見せる余裕もなかったほど、つらい記憶の場所でしかないんだ。なんだ。理由なんて聞くまでもないじゃないか。
黙ったまま、知らないフリをしたまま、明るくアスカを送り出すことが、きっとアスカの幸せだ。
決心した僕は、アスカと過ごす残りの時間を努めて明るく振る舞った。
「ほら、日本もそんなに悪くない」
少しでもアスカがそう感じてくれたなら、アスカはきっとまた日本へ戻ってきてくれるはず。日本を懐かしく思ってくれるはず。きっとまた会えるはずだから。
「アスカ、忘れ物はない?」
今日のミサトさんは、珍しく朝からアスカの世話ばかり焼いている。
「もう、さっきから何度同じこと聞くのよ。ないわよ。大丈夫よ」
アスカは両腕で段ボール箱を抱え、大きなスーツケースをお尻で押しながら部屋から出てきた。
「はい。これもお願いね」
そう言って当たり前の顔で抱えていたダンボール箱をドサッと僕に押し付けた。これも明日発送する荷物と一緒にしておけということらしい。
アスカは今日、日本を経つ。夕方17時のフライトだ。もうすぐ家を出なければならない。
僕はこの数日、ずっと考えていた。最後にアスカに言うべきことは何だろうかって。
「今までありがとう」とか「ドイツに行っても元気でね」とか、そんなどこにでもあるような言葉じゃいけないと思うんだ。アスカと僕はそんな薄っぺらな関係じゃないと思うから。そう思っているのは僕だけで、アスカは僕のことを疎んじているかもしれないけど。
それでもやっぱり僕にとってアスカは特別な存在なんだ。一緒に戦い命懸けの苦しみを共有した仲間。そして、ほんの短い間だけど空間と思い出を共有した家族だから。
そんな大切な人にかける言葉って一体何なんだろう。僕がアスカに伝えたいことって何だろう。
「さあアスカ、そろそろ出発するわよ」
ミサトさんは右手の人差し指にひっかけた車のキーを、カチャンと音を立てて手のひらで握りしめた。
「だからいいってば。わざわざ空港まで見送りに来てくれなくて大丈夫だから」
「そんなこと言わないの。これでもアスカがいなくなることになって、私悲しんでるのよ。飛行機が飛び立つまで見送らせてよ」
その言葉の通り、今日のミサトさんは朝から落ち着かず、邪魔にされるほどアスカの周りをウロウロしていた。
アスカも当然それは気づいているはずなのに、見送りだけは頑なに拒んでいる。
「最後なんだから」
「辛気臭いのは嫌なのよ。だから見送りはいらないわ」
「そんなぁ」
しおらしく肩を落としたミサトさんはなんか一回り小さく見えたけど、アスカはそんなことにも動じず着々と身支度を終えていた。
「さてと」
アスカはボフっと音を立てて大きなボストンバッグを玄関の床に置くと、くるりと僕たちを振り返った。
「アタシそろそろ行くわ」
「本当に行っちゃうのね」
「ええ。これで日本の狭ーい家ともお別れ。まあコンパクトで機能的っていうか、そんなに嫌いじゃなかったけど」
「またそんなこと言って、本当は寂しいくせに」
「バカ言わないでよ。寂しいわけないじゃない。バッカじゃないのっ」
ふざけて擦り寄るミサトさんの手を、アスカは決して振り払ったりしなかった。少しも嫌がっていなかった。
日本の生活を好きになれなかったアスカも、ミサトさんと別れるのは寂しいのかな。子供の頃からの知り合いみたいだし、なんだかんだ言っても二人は仲良いんだ。ミサトさんもそれはわかっているから、わざとふざけてそんなこと言ったりして。
「いつでも帰ってらっしゃいよ」
「わかってるわよ」
「アスカ、行ってらっしゃい」
「うん」
ミサトさんはアスカをギュッと抱きしめた。
「それじゃあ」
ミサトさんからそっと身体を離したアスカは、次に僕を振り返る。
いよいよ僕の番だ。アスカとの別れの挨拶だ。そう思ったらなんだか照れくさくなって、右手の人差し指でおでこを少し掻いて顔を上げた。その時だった。
「シンジはこれとこれね」
「へっ?」
アスカは僕の顔ではなく自分の大きなスーツケースとボストンバッグに目を遣っている。
「へっ?」
何を言われてるのかサッパリわからない僕は、もう一度素っ頓狂な声を上げてしまった。
「だから、これとこれ」
「へっ?」
「だーかーらー」
全く意味がわからなくてキョトンとしてる僕に業を煮やしたらしいアスカは、足元の大きなボストンバッグとそのすぐ近くの壁際に置いてあるスーツケースをこちらに向かって押し付けてきた。
「これが何?」
「アンタ馬鹿? アタシ一人でこの荷物を空港まで運べると思ってんの? 他にもまだ荷物あるのよ?」
「だから?」
「だから? もう本当に鈍いわね。空港まで荷物を運ぶに決まってじゃない」
「えっ、僕が?」
「他に誰がいるのよ?」
「だってさっき見送りはいらないって」
「見送りじゃないわ。荷物運びよ」
アスカはさも当たり前だと言わんばかりに、大きく肩をすくめた。
「アスカ、重い荷物を持って空港まで行かなくても、車で送ってあげるわよ」
「シンジに運ばせるから大丈夫よ」
「でも私も……」
そう言いかけたミサトさんはアスカの顔と僕の顔を見比べて、なぜか一人で納得したようにニヤリと小さく頷いた。
「そう、じゃあシンちゃんお願いね」
なんでミサトさんがそんなに嬉しそうに笑っているのか僕には検討もつかなかったけど、それでも僕もアスカとここでお別れしてしまうのはとても寂しい気がしていたから、荷物運びに反対する理由はなかった。
「あ、はい」
素直に頷いた僕に、アスカはとても満足そうだった。
***
ガタタタン ガタタタン ガタタタン
僕とアスカは東日本第二国際空港に向かう電車に揺られていた。
東日本第二国際空港は第三新東京市から直線距離で50kmほどの位置にある。かつてそこは静岡市と呼ばれていたらしい。
第三新東京市から東日本第二国際空港までは直通電車があるので、それに乗ってしまえば、僕らはただ車輌に揺られていれば良かった。
赤い海から戻ってきてまだそれほど長い時間を経ていない今、海外へ旅行しようという人はほどんどなく、空港利用者の多くがビジネスを目的としている。そのため、空港へ向かうこの電車内も、僕らの他にはスーツ姿の人がチラホラいるだけだった。
静かな車内で僕とアスカは少し間を空けて座っている。自分で僕について来いと言ったわりにアスカは何を話すわけでもなく、ただじっと車窓を見つめていた。
アスカはどんな想いで窓の外の景色を眺めているのか。「もうこれで日本ともお別れ」そんなことを考えているのかもしれない。
アスカの日本での思い出って何だろう?
苦しかったこと? 辛かったこと? 悲しかったこと? 寂しかったこと?
アスカにとって日本は不幸な思い出しかない、記憶から消してしまいたい場所なのだろうか?
ほんのひと時でも楽しかったと思える瞬間があったなら、日本での嫌な思い出も少しはマシなものになると思うのに。
僕は目だけを動かしてチラッとアスカの様子を窺ったけど、アスカは変わらず前を見つめたままだった。
自分勝手かも知れないけど、ミサトさんや僕や学校のみんなと過ごした時間は無駄ではなかったと、アスカにはそう思ってもらいたい。僕はアスカと過ごした日々のどんなことも全部忘れられないし、忘れちゃいけないと思ってる。きっとそれが今の僕にできる最大限の罪滅ぼしだと思うから。
でもそれだけじゃない。楽しかった日も、辛かった日も、苦しかったときも、いがみ合った日も、僕はアスカと過ごした全部が嬉しくてたまらないんだ。
「アスカ」
「ん?」
僕の呼びかけにアスカはわずかに顔を傾け僕を一瞥すると、また正面に視線を戻した。
「アスカはさ」
「……」
「アスカは日本に来たこと、後悔してる?」
「後悔?」
「うん。後悔」
「そんなこと聞いてどうするの?」
怒るわけでもなく呆れるわけでもなく、アスカは正面を向いたまま、僕の質問にあくまでも冷静だった。
「どうするって僕はただ……ただアスカが日本に来てから大変なことばかりだったから、もしかしてアスカは日本に来たことを後悔してて、それで急にドイツに帰ることにしたんじゃないかってずっと気になって」
「まあね」
「そっか。やっぱりそっか」
「でもそれだけが理由じゃないわ」
「じゃあ、何で?」
「何で?」
この電車に乗り込んでから、初めてアスカが僕の方に顔を向けた。何も言わずじっと僕を見てる。それもすごく寂しそうな、辛そうな、そんな瞳をして。
このとき見たアスカの表情が、なぜか僕にはアスカの想いの全てのように感じられた。アスカは言葉では何も言わなかったけど、つまりそれが答えなんだと僕にはわかった。
そうか。やっぱり僕のせいなのか。僕のことがまだ許せないんだね。僕のことが嫌いだから、だからドイツへ帰るんだね。ミサトさんや学校のみんなと離れる決断をさせてしまったのは、僕なんだね。
アスカ、ごめんね。
アスカの心の内に気づいてしまった今、僕がアスカにかけられる言葉なんて何もない。僕の言葉は慰めにも励ましにもならず、アスカを苦しめるだけのもの。もうこれ以上アスカを苦しめてはいけない。
僕たちは再び静かに正面を向いた。
間もなくして僕たちを乗せた東日本第二国際空港駅ゆきの電車は、ついに目的地に到着した。
電車を下りてからも僕たちは黙ったまま、アスカが前を僕が少し後ろを、僕がアスカについて行くように歩く。
アスカの後ろを追いかけるように歩きながら、なんだか可笑しくなってきた。
こんな風に気まずい気分でアスカと一緒に歩くのももう最後なんだな、なんて。こんなことを寂しく感じてしまう僕はちょっとおかしいのかもしれない。
思わず顔が綻んだ。
「何?」
僕の異変に気がついたのか、アスカが不審そうな顔をして振り向いた。
「え? あ、何でもないよ」
慌てて手を振り平静を装った僕に納得はしていないようだったけど、アスカは「ふーん」とだけ言って、再び僕の前を歩きだした。
あと少しでこの後ろ姿ともお別れか。明日からはきっと毎日が静かに淡々と過ぎてゆくんだろう。
アスカとケンカしたり、アスカに怒られたり、ふくれっ面したアスカとご飯を食べたり、もうそんなこともできなくなる。
そんなアスカとの関係に正直嫌気が差したときもあったけど、今はただただ寂しい。
アスカは今日ドイツへ帰る。
アスカが僕の前からいなくなる。
***
「空港ってこんな風になってるのか」
そんなことを思いながら電光掲示板を見上げる。
僕は海外へ行ったことがないから、というか第三新東京市とそれまで住んでいた町しか知らないから、こんな風に世界と繋がっている場所にいるということがとても不思議だった。
もちろん海外に向かって飛び立つのは、僕ではなくアスカなんだけれども。
いつか僕にもこの場所から外の世界に飛び立つ日が来るのだろうか。
いや、僕はいくつになっても平凡な日常を生きているんじゃないだろうか。きっとこんな場所に縁はない。
でもいつか、アスカの生まれた育った街に行ってみたいと思う。アスカがどんな景色を見て何を感じて、どんな空気の中で何を思って生きてきたのか、それを感じることができれば、ほんの少しだけでもアスカに近づくことができるかもしれないから。
ベンチの端に座って電光掲示板を見上げていると、まるでこの場所がこちらの世界とあちらの世界を遮る境目のような気がしてくる。つまり僕が残される狭い世界と、アスカが出て行く広い世界だ。狭い社会で生きてきた僕は、少し怖くなった。広い世界に何があるんだろう。アスカはまた戻ってきてくれるだろうか。
「アンタは?」
「えっ?」
ボーっとしていた僕は、不意をつかれた。
アスカの声は少し苛立っているようにも聞こえ、そして心の内を表すかのように、アスカは足元のボストンバッグをボスッと軽く蹴飛ばした。
「さっきアンタはアタシに日本に来たことを後悔しているかって聞いたけど、アンタはどうなのよ? ネルフに来たこと、後悔してるの?」
「僕?」
思いがけない質問だった。僕が第三新東京市に来たことを後悔しているかなんて、そんなこと改めて考えたことなかった。
後悔? どうだろう?
突然父さんに呼ばれて訳のわからないままにエヴァに乗せられて、苦しいことばっかりで辛いことばっかりだったけど、でもそれも少しずつ変わっていった気がする。
ミサトさんの家にお世話になって、そこにアスカが加わって、トウジやケンスケやいろんな人たちと出会って、もちろん苦しいことも辛いことも数え切れないくらいあったけど、でもそれだけじゃなかった。
そこには楽しいことも嬉しいことも少なからずあったから。そして赤い海から帰ってきた今は、これで良かったんだと思っている。それまでのすべての経験があるからこそ、今の僕がいるのだと思うから。
僕はもう後悔はしていない。これが正直な気持ちだ。
「今はもう後悔してないよ」
「今は?」
「うん。今は」
「じゃあ前は後悔してたってこと?」
「うん」
「そりゃそうよね。アンタみたいな弱気な人間が後悔しないわけないもの」
アスカは僕の答えが自分の想像通りであったことに納得しているのか、2回ほど小さく頷いた。
「でもね」
僕の声にアスカがゆっくりと振り返る。
「今はもう後悔してないよ。だって」
アスカは僕の真意を図りかねているのか、不審そうな顔つきで首を傾げていた。
「アスカに会えたから」
一瞬、アスカの目が大きく見開いたように見えた。
「それまでの僕の生活は辛いことや苦しいことばかりだったから、いつも逃げ出すことしか考えてなかったんだ。でもね、今は違うよ。アスカとか綾波とか、ミサトさんや加持さん、それにトウジやケンスケ。みんなに出会えて、みんながいてくれて、とても楽しかったしそれに嬉しかった。僕はここにいてもいいんだって、初めて思えたんだ。だから嫌なこともいっぱいあったけど、今はもう後悔してないよ」
ずっと黙って話を聞いていたアスカはしばらく僕の顔を見つめていたけど、急に顔をゆがめてプイッと横を向いた。
「アンタは気楽でいいわね」
とても小さな声だったけど、僕は聞き逃さなかった。
そっか。アスカは後悔してるんだね。今までの生活はアスカを苦しめただけだったんだね。
所詮僕はアスカの怒りの対象。憎むべき相手。僕のしたことはアスカを怒らせることはあっても、助けになることなんて何もなかったんだ。
ごめんね。本当にごめんね。
辺りがざわめき出した。そういえば少し前から人の往来が増えた気がする。足早に出国審査口へ駆け込む人、別れを惜しむようにいつまでもそこに佇んでいるカップルや、新たな旅立ちに目を輝かせている若者等が目に入ってきた。
サードインパクトから間もないというのに、こんなにも多くの人が世界へ向かって飛び立とうとしていることに驚く。空港へ向かう電車内では人も疎らかと思ったが、実際はこんなにも人々が世界を飛び回ってるのだ。人間て逞しいんだな。僕はさっきからそんなどうでもいいことばかり考えていた。アスカと共有できる時間は残り少ないというのに、僕はただそこにいることしかできないでいる。
アスカも僕の隣りで何をするわけでもなく、ただそこにいた。
お互いこれが最後だということは十分にわかっているけれど、だからといってどうしたら良いのだろう。何をすべきかも、何を言うべきかもわからない。
これじゃアスカにとって、僕は最後までバカシンジのままだ。
そんなもどかしい沈黙を破ったのは、僕ではない。やはりアスカだった。
「そろそろ行くわ」
不意に立ち上がったアスカが、勢い良く僕の方へ手を伸ばした。
「えっ? な、何?」
突然のことに戸惑っている僕に、アスカは明らかにムッとした顔をしている。そんな僕を尻目にさらに腕をグイッと伸ばすと、僕の足元に置いてあったボストンバッグを持ち上げた。
ほんの一瞬だけど、まさかとは思ったけど、僕は最後に別れの握手でも求められたのかと思ってしまった。我ながら勘違いも甚だしい。
「時間だから行くわ。じゃあね、シンジ」
何の前触れもなく急に立ち上がったかと思えば、まるでちょっとそこまで買い物にでも行くかのように、驚くほどあっさりとアスカは僕に背を向けようとしている。
「えっ、あ、ちょっと待ってよ、アスカ」
急いでベンチから立ち上り、ついには前のめりになりながら、僕はアスカに慌てて駆け寄った。
「も、もう行っちゃうの?」
こんな素っ気なく?
「もうすぐ搭乗時刻だもの」
そう言いながら、アスカは頭上の電光掲示板を見上げた。すぐそこで出発時刻を告げている電光掲示板が、僕にはなんだか手招きしているように見える。
「そうだけど」
確かに時間は迫っている。誰よりも時間を気にして、さっきから腕時計を何度も確認している僕が気づいていないわけがない。
頭ではわかってるんだけど、これがアスカと過ごす最後の時間だと思うと素直に送り出すことができないんだ。
「何? 何か用?」
「いや、そうじゃないんだけど」
「そ。それじゃ」
「えっ、ちょっと待ってよ。アスカ、待ってよ」
「だから何よ?」
再三の僕の呼びかけにアスカが少し苛つき始めた。
何て言えばいいのか。アスカとの別れを、僕の心はまだ受け入れられてないみたいだ。別れの言葉を伝えたいのに、口から何も出てこない。
でも言わないと。アスカに言わないと。
「アスカ」
「だから何よ?」
「その、あれだよ。これで僕たち、しばらく会えないんだなと思って」
「そうね」
絞り出した僕の問いかけは、どうでもいいわかりきったことだった。そのせいかアスカの返答もひどく素っ気ない。
「アスカは今度いつ日本へ帰って来るの?」
「さあ」
「さあって、アスカはもう日本へ来ないつもりなの?」
「そんな先のことわかるわけないでしょ」
「そんな……そんな寂しいこと言うなよ。みんなアスカにまた会いたいと思ってるんだから」
「さあ、どうかしら?」
「本当だよ。アスカがドイツに帰っちゃうって聞いて、みんなすごく悲しんでたじゃないか。だから帰ってきてよ。また会いに来てよ。みんな待ってるんだから。頼むよ、アスカ」
「わかった。わかったわよ」
あまりに素っ気ない返事をするアスカに、思わず突っかかるように畳み掛けてしまった。こんなのが別れの挨拶だなんて、我ながらなんて馬鹿なんだろう。
僕のあまりの剣幕に驚いたのか不意を突かれたのか、アスカは慌てて僕を手で制止した。
「わかったわよ。わかったから。戻ってくればいいんでしょ。帰ってくるわよ」
半ば呆れたような口調だったけど、それでも僕には十分だった。細い糸1本で辛うじて繋がっているような状態かもしれないけど、繋がっている限りこれは完全な別れじゃない。これが僕の唯一の慰めになってくれるに違いない。
出国審査口へ向かうアスカの後を僕が追うように歩く。アスカはもう僕に荷物を預けることはしなかった。大きなボストンバックを自分の肩にかけている。
アスカはまさに飛び立とうとしてるんだ。日本という地から。ネルフから。エヴァから。過去のしがらみから。
「アスカ、いってらっしゃい」
出国審査口でアスカと向き合い、僕は努めて明るく振る舞った。
この入り口を潜れば、アスカは機上の人になる。でも僕はもう湿っぽくなったりしない。だってアスカは少し遠いところへ、少し長い旅に出るだけだから。僕はそう信じてるから。
僕は変わらずここにいる。ミサトさんも、みんなも、ここでアスカを待ってる。だからアスカ、必ず帰ってきて。
「じゃあ、行くわ」
僕の願いが届いているのかどうか、それはわからない。
特に微笑むわけでもなく、かと言って悲しそうな顔をするわけでもなく、普通にあくまでも淡々と、そしてあっさりとアスカは僕に背を向けた。
「あっ」
そんな馬鹿な。せっかくここまでアスカを見送りに来たのに、こんなにあっけない別れだなんて。
ただの荷物持ちだと思って付いて来たけど、そう言いながらも僕は少し期待してしまっていたのかもしれない。アスカが僕だけをここに連れてきたのには、何か理由があるんじゃないかって。
アスカに限ってそんなことあるわけないのに。
あっさりと僕に背を向けたアスカはそのまま出国審査口の入り口を潜り、そしてすぐに見えなくなった。
本当に行っちゃったんだ。残された僕はガックリと肩を落とし、もう見えなくなったアスカの後ろ姿をしばらく眺めていた。
何でも良かったのに。別れの挨拶じゃなくても、僕を罵る言葉でも良かった。何か一言で良かったんだ。
あんまりだよ、アスカ。寂しいよ、アスカ。もう会えないのに、寂しいよ。
でもそれが当然なのかもしれない。アスカは僕から離れたくてドイツへ帰るのだから。そんな僕に向かって、別れの言葉なんてあるわけない。早く離れてしまいたい僕にかける言葉なんてあるわけない。
僕は肩を落としたまま歩きだし、その場を離れた。
さようなら、アスカ。
心の中で繰り返す。
僕はここで待ってるよ。必ず帰って来てね。いつまでも待ってるから。アスカ、またね。
暗い顔してミサトさんのところへ帰るわけにはいかない。ミサトさんだって寂しいんだ。僕がしっかりしなくちゃ。
そうは言っても、家に帰ればまた現実を突きつけられるに違いない。主のいなくなった部屋と少なくなった洗濯物、座る人のいなくなったイスと二人分の料理しか並ばない食卓、そういうことに僕はどれくらいで慣れることができるのだろう。
アスカのいない毎日。静かで退屈な日常は、想像に難くない。
そんなことを考えた時だった。僕の背中から、ふと声が聞こえた。誰かが僕を呼んでいる。そう。僕の背中の向こうから。聞き慣れた声。忘れたくない声。僕の、大好きな声。
僕はハッと顔を上げて急いで振り向いた。
「シンジ!」
出国審査口の係員の後ろから身を乗り出すようにして、アスカが僕を呼んでいる。
近くを行き交う人たちの視線が僕とアスカに交互に向けられているのがわかったけど、そんなことはどうでも良かった。アスカが僕を呼んでいる。行かなくちゃ。早くアスカのもとに行かなくちゃ。
「アスカ!」
驚いて駆け寄ろうとしていた僕を、アスカは何故か手で制止した。
これ以上近づくなってこと? 自分で僕を呼んだくせに?
おそらく怪訝な顔をしているであろう僕に向かって、アスカはニッコリと微笑み、そして大きな声でこう言った。
「シンジ! In der Lage sein, Sie zu treffen, war ich glucklich!」
「えっ、何?」
僕がドイツ語わからないの知ってるくせに。
僕の戸惑った顔を見てアスカはクスリと肩を竦め、くるりと踵を返した。
「じゃあね!」
えっ? えっ?
アスカは今までに見たことのないような笑顔で大きく手を振り、そしてまた向こうに消えて行った。
一瞬の出来事に呆然としている僕なんかお構いなしだ。
何が起きたのかわからずあっけに取られていた僕も、ハッと我に返ると慌てて出国審査口に駆け寄ってはみたがすでにそこにアスカの姿はなく、またしても僕はひとりポツンと残された。
何だよ、もう。
思えばアスカが日本に来たあの日からずっとそうだった。何にも変わってなかったんだ。初めて会ったその日から今日まで、僕はずっとアスカに振り回されっ放しじゃないか。
僕はひとりで可笑しくなってクククっと肩を震わせた。
呼び止められた理由はよくわからないけど、最後にアスカが笑顔を見せてくれたというだけで、それだけで僕はとても幸せだ。
さあ、帰ろう。
急に晴れ晴れとした気持ちになって、僕は勢いよく振り向いた。
...続く
あとがき
長らくお待たせいたしました。”想起”の完成です。
文中、ドイツ語の文章が出てきますが私はドイツ語さっぱりなので、一生懸命調べたけど、もしかしたら間違えてるかも。
そのときは、ごめんなさい。
私と同様、ドイツ語がさっぱりな皆様、どうぞシンジと同じ心境で「?《となって、最終章をお待ちくださいw
次はいよいよ最終章になります。
やっと終わりが見えてきて、書いてる私も本当に嬉しいです。
あとどのくらいかかるかはお約束できませんが(駄目な作者でごめん)、今しばらくお付き合いくださいませ。
”想起”を最後までお読みくださって、ありがとうございました。
<追伸>
なぜか鍵括弧の閉じる”」”が”《 ”に化けてしまっていたのですが、それはなんとか解消できました。
その代わりというかなんというか、ドイツ語の点々(uの上に付いてたもの)がなくなりました。
もうこれ以上修正する気力がないので、お見逃しくださいませ。
本来記載するべきであった文章をここに貼っておきますね。これでいいよね……